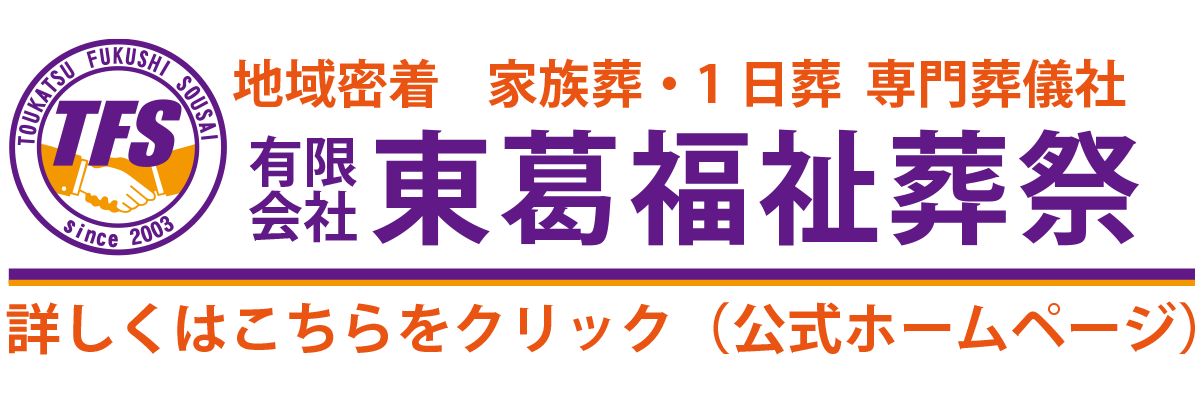お彼岸とは 「お彼岸の時期にはお墓参りに行っているけど本来のお彼岸の意味は分からない・・・」という方も多いかもしれません。お彼岸という言葉は、元々サンスクリット語の「波羅蜜多(パーラミタ―)」を漢訳した「到彼岸」という言 […]
仏事
涅槃会をご存知ですか?
涅槃会とは お釈迦様は仏教の開祖として知られていますが、そのお釈迦様が亡くなられた日をご存知でしょうか?お釈迦様の命日は2月15日と伝えられており、お釈迦様の遺徳を偲び報恩感謝の祈りを捧げるために営まれる法要を涅槃会とい […]
立春と節分
2月4日は立春です 本日2月4日は立春です。立春は二十四節季によって決められた季節を表す名称の1つで、春の気配が立ち始める日、すなわち春の始まりを告げる日です。二十四節季は旧暦に基づいているため、現在の日本で用いられてい […]
忌中と喪中
忌中と喪中の違いは お身内やお知り合いでご不幸があった際に“忌中”や“喪中”という言葉を耳にされたことがあるかと思います。忌中も喪中も故人様の死を悼む期間であるという点では同じですが、本来の意味やそれぞれの習慣、服喪期間 […]
お線香について
お線香の歴史 仏事において、お線香は欠かせないものです。葬儀や法要の際以外にも、日々お仏壇にお参りする際、お墓参りを行う際等、お線香をあげる機会はたくさんあります。お線香の歴史は古く、様々な諸説がありますが、西暦538年 […]
1月7日は松納めです
松納めと松の内 松納め・松の内とは 本日、1月7日は松納めです。松納めとは正月の間に飾った門松やしめ飾りを取り払う日です。松納めは、松下がり、松払い、松直し、松引き等とも呼ばれ、正月の終わりを告げる節目の日となっています […]
平成最後の大晦日
大晦日の由来 本日12月31日は大晦日です。来年は元号が変わることもあり、平成最後の大晦日ということになります。大晦日とはいうまでもなく1年の最後の日ですが、なぜ“大晦日”というのかご存知ですか? “晦”は月の満ち欠けを […]
星まつりをご存知ですか?
星まつりとは 星まつりは「星供(ほしく)」「星供養(ほしくよう)」とも呼ばれる仏教行事です。古来より人の営みは天体の動きと密接に関係していると考えられていました。人の営みは、生まれながらに定められた本命星(ほんみょうじょ […]
“お坊さん”に声をかけるとき
なぜ“お坊さん”と呼ぶの? 普段から何気なく使っている“お坊さん”という言葉、一般的に仏門に入った僧侶を表す言葉として使われていますが、なぜ僧侶のことを“お坊さん”と呼ぶのでしょうか。 その昔、奈良時代から平安時代の都城 […]
成道会をご存知ですか?
成道会はお釈迦様が悟りを開いた日を記念する仏教行事です お釈迦様は仏教の開祖として広く知られていますが、そのお釈迦様が悟りを開いた日を記念して行われる法要を成道会(じょうどうえ)といいます。“成道”とは悟りを開かれたこと […]